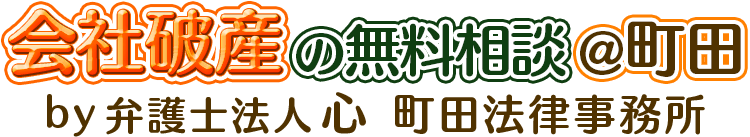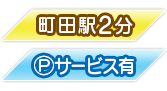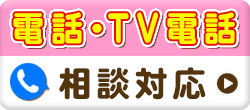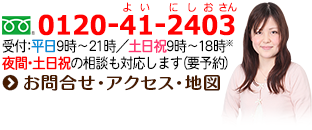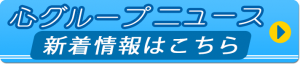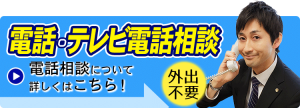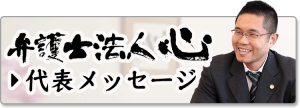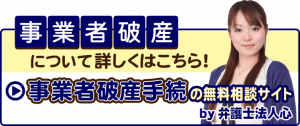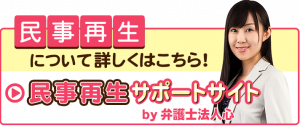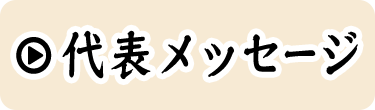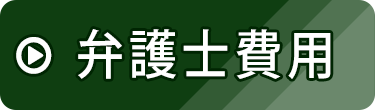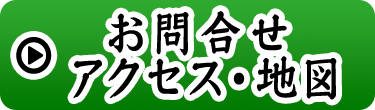法人破産の流れと失敗しないための注意点
会社の経営が立ち行かなくなったときに行われる法的な手続きが「倒産」です。
倒産には様々な種類がありますが、そのなかのひとつとして「法人破産」が選択されることがあります。
法人破産というと「会社がなくなること」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
以下、法人破産が会社に及ぼす効果や、法人破産の手続きの流れについて説明します。
1 法人破産手続きの効果・目的
法人破産とは、法人の財産を処分・清算して、会社の法人格を消滅させる手続きです。
法人破産をすると、裁判所が選任した「破産管財人」が、会社の財産や債権債務・契約関係などを調査します。
そのうえで、取り立てるべき債権は回収し、会社の財産を処分してお金に換え、税金や従業員の賃金などの債務を支払います。
その後、残った資産を各債権者に配当し、会社を消滅させます。
したがって、法人破産した会社は、債務を支払う必要がなくなります。
債務超過に陥った会社が法人破産をすることで、会社の消滅と引き換えに、債務も消滅させることができるのです。
2 法人破産手続きの流れ
次に、法人破産の手順について、一般的なケースを用いて説明します。
目安となる期間についても記載しますが、案件の難易度や裁判所の運用によってある程度異なります。
⑴ 弁護士に相談し、依頼する
まず法人破産について、弁護士に相談や依頼をします。
弁護士はヒアリングを通じて様々な検証を行い、会社の債務問題の解決方法として法人破産が適切な手段であるかどうかを検討します。
なお、弁護士に依頼をしないと、少額管財制度を利用できません。
⑵ 弁護士が受任通知を発送
法人破産の依頼を受けた弁護士は、債権者に「受任通知」という書類を送付します。
これを受け取った債権者は、以降は代理人である弁護士を介してやりとりをすることになります。
依頼者の立場からすると、弁護士が債権者との窓口になります。
結果として、債権者からの直接の催促に悩まされることが亡くなります。
ただし、金融業者以外の債権者、特に個人債権者については必ずしも催促を止められないという点には注意が必要です。
⑶ 会社の財産や権利関係等の調査
弁護士が決算書などの帳簿を精査し、依頼人からヒアリングを行うなどして、会社の財産・債権・債務・契約関係などを詳しく調査します。
また、債権者の中に貸金業者等が存在する場合は、問い合わせて過去の取引履歴を開示してもらいます。
もし過払い金が発生している場合は、過払い金の返還請求を行います。
⑷ 会社の財産を保全(財産調査と同時進行)
破産手続きでは、会社の財産が処分されてお金に換えられます。
それらは滞納した税金や従業員への未払い賃金の支払いに充てられ、残りは債権者に配当されます。
そのため、会社内の人や債権者、取引先などが勝手に会社の財産を持ち出したり処分したりすると、従業員や債権者が本来得られたはずのお金を得られなくなってしまいます。
これを防ぐためには、会社の財産を保全しなければなりません。
例えば以下のようなことが行われます。
・会社の通帳、決算書、印鑑、不動産関係の権利を表す書類等、財産に関する重要なものを弁護士が直接管理
・商品在庫や小切手、手形等を弁護士が確保
・会社や倉庫等への侵入防止策の構築
・(必要に応じて)従業員の解雇など
⑸ 破産申立て書類の準備
法人破産は裁判所に申立てをして行うため、裁判所に提出する書類を揃えます。
例えば、以下の書類が必要となります。
必要な書類や資料は事案によってある程度異なるので、弁護士の指示を受けながら書類の収集等を行うことになります。
・破産申立書
・債権者一覧表
・財産目録
・決算書等の会計書類
・商業登記簿謄本や登記事項証明書
・不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本と、その価値を証明する書類
物件を賃借している場合は賃貸借契約書
・その他、財産を証明する書類(通帳や有価証券など)
⑹ 裁判所へ申立て
裁判所に法人破産の申立てを行います。
法人破産が妥当であると裁判所が認めた場合、破産手続の開始決定が行われます。
なお、破産手続開始決定に先立って、裁判所で「破産審尋」が行われることがあります。
破産審尋では、裁判官が法人の代表者に、破産に至った経緯や法人の資産および負債についての聴取等を行います。
⑺ 管財業務
裁判所が「破産管財人」という、破産手続きの実務面を執り行う人を選任します。
破産管財人は法人の代表者にヒアリングを行い、破産に至った経緯や法人の資産状況、既に処分した資産があれば処分の理由や経緯などを把握します。
その後、破産管財人は売掛金等を含めた会社の債権を回収し、会社の財産を売却して現金化していきます。
破産申立人は破産手続きに協力する義務があるため、破産管財人の指示に従って会社の資産や負債を示す資料などを提示しなければなりません。
⑻ 債権者集会
裁判所で債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人が業務の進捗を報告します。
集会には破産申立人が出席しなければなりませんが、代理人弁護士も同席できますので、ご安心ください。
また、債権者の出席は任意であるため、実務においては欠席する債権者もいます。
債権者集会は、特に問題がなければ数十分程度で終わることもあります。
事案によっては、複数回債権者集会が行われることもあります。
⑼ 破産手続の終了
法人の資産がなく、債権者へ配当するものがない場合は、裁判所が債権者集会で破産手続きの廃止決定を行います。
もし配当がある場合は、債権者集会で配当期日が決定されます。
期日に配当が終了すると、裁判所が破産手続きの終結決定を行い法人破産の手続きは終了します。
3 法人破産の流れで注意すべきこと
法人破産には、注意すべきことが多くあります。
以下、法人破産に失敗しないために債務者が特に注意すべきことについて説明します。
⑴ 一部の債権者を優遇するような返済はしない
特定の債権者に迷惑をかけたくないからと、破産の前に一部の債権者にのみ債務を弁済したいとお考えの方もいらっしゃいます。
例えば「親からお金を借りて会社を作ったけど経営に失敗した。親に迷惑をかけたくないから親への借金だけは法人破産の前に払ってしまおう」と考えるケースです。
しかし、破産手続きにおいては、すべての債権者が平等に扱われるという原則があります。
もし一部の債権者にのみ債務の弁済が行われてしまうと、それによって法人の資産が減ってしまい、他の債権者が配当を受けられなくなるからです。
仮に一部の債権者のみに対する弁済が行われた場合、破産管財人は、破産手続きの前に弁済された財産を、弁済を受けた人から取り戻すことができます(否認権の行使)。
もし偏頗弁済を受けた人が破産管財人の請求に従わない場合、破産管財人が訴訟を起こすなどして事態が複雑化するおそれがあります。
つまり、迷惑をかけたくなくて、偏頗弁済をしたはずなのに、逆にその偏頗弁済の受けた人に、大きな迷惑をかけてしまうことになります。
このような事態に陥ることを避けるためにも、破産を検討する段階から弁護士に相談し、自己判断による弁済は行わないようにすることが大切です。
⑵ 法人の財産を自己判断で処分しない
法人破産の前に「どうせ破産したらなくなってしまうから」と、法人の財産を他人へ譲渡したり、安く売ったり、処分したりしてはいけません。
不当に処分されたと判断される財産がある場合、破産管財人がその財産を取り戻すための手続きを行います。
「事情を知らない相手へ相当の対価で財産を売却する」ことは問題ないとされています。
例えば、破産費用を捻出するために、法人で加入している保険を解約するケースです。
しかし、自己判断で行うと後で問題になる可能性もあります。
財産の売却や処分についても、事前に弁護士に相談してから行うようにしましょう。
⑶ 法人破産のことを迂闊に公言しない
従業員や取引先に「実は破産を考えている」などと伝えることは、おすすめできません。
従業員や取引先が慌てて法人の財産を持ち出したり、債権者が押しかけたりするなど、不要な混乱を生じさせるおそれがあるためです。
信用のある人にのみ相談しても、その人から外部に漏れる可能性がないとは言い切れません。
従業員等に告げるタイミングについても、事前に弁護士に相談をしましょう。
⑷ 破産費用を確保しておく
法人破産には弁護士費用、裁判所に納める費用、破産管財人の報酬などが必要となります。
法人の規模や債務額、債権者数などによって変動しますが、個人の自己破産より高額になることが多いです。
破産するためのお金を確保しておかなければ、破産をすることができません。
そのため、可能な限り資金に余裕のある段階で弁護士に相談することも大切です。
4 法人破産は弁護士に相談が必須
法人破産は、会社とともに会社の財産や債務をすべて消滅させる手続きです。
取引先などとの契約が多いため、法人破産は個人の破産と比べて複雑な処理が必要となります。弁護士に依頼して処理や手続きを代理してもらいましょう。
法人破産には注意すべき点が多く、また少額管財を利用するためには、弁護士への依頼が不可欠です。
会社の債務に関する問題は、時間の経過とともに悪化していく傾向にありますので、お早めに当法人の弁護士にご相談ください。